 |
||||||
| アラスカシロカモメ(Larus hyperboerus barrovianus)とはシロカモメ(Larus hyperboerus hyperboerus)の亜種でアラスカ北東部を中心に繁殖し、冬季は主に日本近海に南下し、東日本の沿岸でも多数が越冬しているのではないかと考えられている大型カモメです。barrovianusはシロカモメの亜種の中で最も小型で、日本で主に越冬するシロカモメ(pallidissimus)と比べてかなり華奢なので、日本では希なアイスランドカモメとよく間違われます。少し前まではこの亜種の冬季の越冬地についてはほとんど知られていませんでしたが、最近アラスカで発信機をつけられたbarrovianusが北海道襟裳町や稚内市に渡来していたことが明らかになり、さらに東日本の主に太平洋側では小型のシロカモメが多数見つかっていたことから、それらはbarrovianusでありbarrovianusの主要な越冬地は東日本の特に太平洋側であるのではないかと考えられるようになりました。 日本で多数が越冬するシロカモメ(L.h.pallidissimus)はシロカモメの亜種の中で最も大型、背の羽色が最も淡色、初列風切は短い、体格はごつく、嘴がかなり大きい、といった特徴を示します。実際にpallidissimusと思われる個体は大型カモメの中でもひときわ大きく目立っていることが多いです。一方で、barrovianusはシロカモメの亜種中で最も小型、背の羽色は最も暗色、初列風切も長く、嘴も細めといった特徴をもつようです。よって典型的なbarrovianusとpallidissimusだとある程度までの識別は比較的簡単だと思われますが、個体差などを考えると同じ種の亜種を確実に見分けることはほぼ不可能でしょう。しかし、確かに微妙な個体も存在しますが、個人的にはかなり明瞭な差を感じることも多く、やはり日本で観察される小型のシロカモメの大多数はbarrovianusであると考えています。 |
||||||
|
||||||
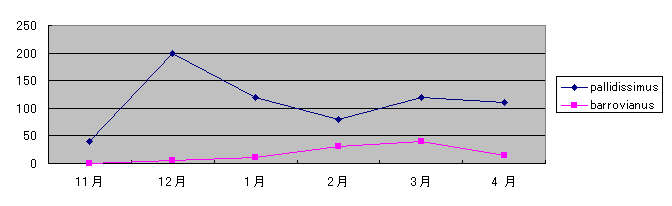 データはかなり古くて苫小牧〜むかわ町における03年10月〜04年3月のものですが、とりあえずこんな感じです。印象通りbarrovianusは春先にかけて増加することは確かなようですが、ここ数年は3月でもそこまで多く観察されなかったり、12月に10羽ほどが見られたりと、渡来傾向は特に一定ではないようです。 また、pallidissimusは道央以南での東日本でもまとまった数が見られる場所はあまりないと思われますが、barrovianusに関してはかなり南の方まで多くの個体が南下しているような気がしています。はっきりしたことはいえませんが、道南砂崎岬や茨城・千葉の利根川河口域などでは小型のシロカモメが多かったり、道央でも春先に個体数が増すのはそういったことと関係しているのかもしれません。 |
||||||


